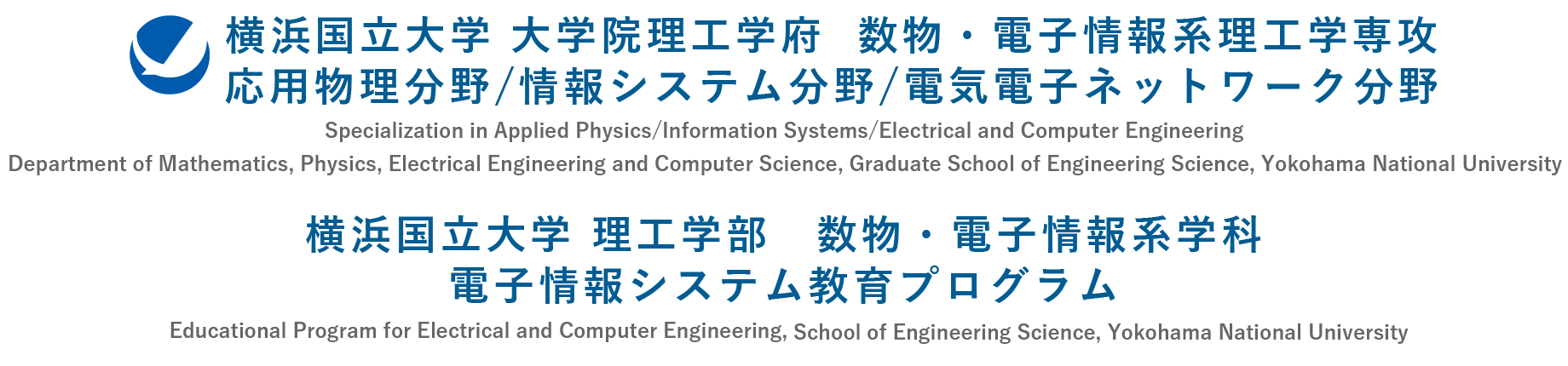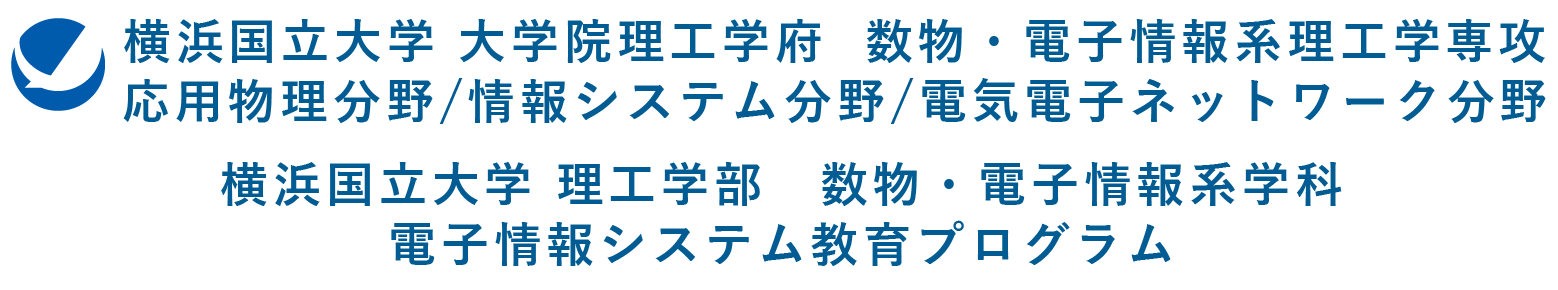「教員の写真」は理工学部教員総覧,「研究室名」は各研究室の詳細情報,「研究室ロゴ」は各研究室のHPにリンクされています.
水平方向にスクロールできます。
 |
赤津研究室 Akatsu Lab |
 |
電気機械エネルギー変換工学(特に回転機)、パワーエレクトロニクス、制御工学 |
赤津研究室(M&Eエネルギー変換研究室) 電気エネルギーを機械エネルギーに変換するモータの消費電力は日本の消費電力の約54%を占めています。古くから日本にあるすべてのモータ効率を1%向上させれば電子力発電所1基分の電力が低減できると言われています。最近ではHEV/EVの発展に伴い、モータの高効率化は燃費/電費に直結するためますます重要になってきています。 モータの高効率化を達成するにはモータだけの高効率化だけではだめで、モータに電力を供給するインバータの高効率化も必要となります。さらにただ回転させるだけのモータ制御ではなく、より緻密に、ミクロな視点からみたモータ制御が必要となってきており、モータ・インバータ・コントローラすべてを統合的に考えた駆動システムが必要となっています。さらに日本の競争力を維持するためには、もう一つ上の段階、例えば静粛性や安全性、信頼性が高い駆動システムを構築することも重要です。これらは日進月歩の世界でありますが、常にトップを走り続けることが重要です。 我々の研究室では、高付加価値をもったモータ技術を実現するために、EV用の新しいモータや、産業用、電動工具用のモータまで、従来の「単なる回転機」とは一味違ったモータを研究しています。そのために材料から絶縁、放熱、振動、制御、通信までを手がけ、少しでも省エネに貢献できるよう心がけています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
荒川研究室 Arakawa Lab |
半導体工学,電子材料工学,量子効果デバイス,光デバイス | |
荒川研究室 (半導体フォトニクス工学研究室) 今日の情報通信社会の発展に伴い、それをハードウエアの面から支えている半導体を中心とする電子・光デバイスの重要性がますます高まっています。より速く、より小型で、より消費電力を小さく、という社会の要求に対応していくためには、現在ある技術の改良だけでは限界があります。 本研究室ではこうした限界を打破するため、シリコンや化合物半導体のナノテクノロジーを用いて、高度な機能や高い性能を有する新しい光の強度,経路,波長などの特性を自在に制御する素子および光集積回路、光素子を用いた高感度センサーの研究開発、電子・光デバイス作製のための微細加工プロセスの研究に取り組んでいます。他大学や他研究機関との共同研究も積極的に進めています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
石川研究室 Ishikawa Lab |
 |
移動体通信、無線信号処理、時空間符号化 |
石川研究室 (ワイヤレスネットワーク研究室) 石川研は2020年4月に誕生しました。研究テーマとして「次世代無線通信」を掲げ、無線通信全般に関して萌芽的な技術を中心に探求しています。高速移動体通信や省電力技術に一定の実績があり、新しいアイディアの提案とその解析により積極的な論文発表を目指しています。詳しくは研究室のウェブサイトをご覧ください。 研究プロジェクト
|
|||
 |
市毛研究室 Ichige Lab |
信号処理,数値解析,電磁界解析,無線通信,画像処理 | |
市毛研究室 (ディジタルセンシング研究室) 音楽,画像,映像,放送,通信など,ディジタル技術は我々の生活の様々なシーンに関わっており,ディジタル信号を取り扱うための信号処理の知識はエンジニアとして必要不可欠なものとなっています.実際,卒業して会社に就職すると,こうした知識が必要になる場面が多いそうです. コンピュータや携帯電話などのディジタル機器では,実際にはどのようにディジタル信号を扱っているのでしょう.これらの機器は,連続的に変化する信号(アナログ信号)をそのままの形では扱えませんので,アナログ信号を標本化(サンプル),量子化,さらに符号化して,ディジタル信号として扱います.こうした処理が信号に与える影響を正しく理解したうえで,回路や機器の設計・制作を行うことが求められます. 本研究室では,ディジタル情報を取り扱うための信号処理の知識を基盤として,スパース正則化や最適化手法の知識,DSP(ディジタルシグナルプロセッサ)上での実装技術などをもとに,移動体通信,画像処理,音声・音響信号処理,適応信号処理などの幅広い応用研究を行っています. |
|||
 |
大矢研究室 Oya Lab |
機能的ナノデバイス,自然・生物の挙動に学ぶ情報処理,カーボンナノチューブ複合紙,カーボンナノチューブ複合糸(布) | |
大矢研究室 (集積ナノデバイス研究室) 本研究室では一風変わったアプローチから“斬新な”ナノ材料やナノデバイスの創生・応用展開・システム構築を目指し2本柱で研究を進めています。一つ目の柱は「自然界に学んだ情報処理のナノデバイスへの実装」であり、もう一つは「伝統技術との融合によるナノ複合材料の開発と応用展開」です。 自然界ではあらゆるものが誰の手も借りずその形をつくりあげ、また様々なものが相互に影響し合うことで高度な情報処理を行っていると考えられます。このように自然界で日々起こっている物理現象を電子デバイス(特にナノデバイス)の物理と対応付けをすることで既存の集積回路とは全く違う、かつ「そのデバイスだからこそ」と言えるような新情報処理デバイスを生み出すことが可能となります(図1)。また、斬新なナノ複合材料の研究も進めています。ここではナノテク材料としてカーボンナノチューブ(CNT)に着目をし、これを利用した複合材料の開発と応用展開を進めています。CNTは多機能で非常に有用ではありますが使用するには少し工夫が必要です。 本研究室では(例えば)日本伝統の和紙作製技術を利用し、紙とCNTを混ぜ複合紙(CNT複合紙)もしくは糸とCNTを複合しCNT複合糸(布)とすることでCNTの新たな応用分野を開拓しています(図2)。一例として、「紙のトランジスタ」が構成可能で、紙状でありながらトランジスタとしての動作をすることを確認しています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
大塚研究室 Otsuka Lab |
 |
マルチモーダル情報処理、社会的信号処理、機械学習、ヒューマンコンピュータインタラクション |
大塚研究室 (マルチモーダル情報処理研究室) 「以心伝心」や「場の空気を読む」といった微細な心の機微までも理解できる「社会的知性」を備えた人工知能の実現に向け,本研究室では,カメラやマイク,センサなどを介して観測される複数モダリティのデータ(画像,音声,言語,運動など)を統合することで,実世界で生じる様々な言語・非言語情報を読み解き,人の内的状態(感情,意図,個性など)や他者との関わり(社会的相互作用)などを自動的に認識・推定する技術の研究を進めています.このような研究分野は「マルチモーダル情報処理」や「社会的信号処理」と呼ばれるフロンティア領域として近年,注目を集めており,画像認識や音響信号処理,自然言語処理,機械学習,深層学習,感性情報学,社会言語学,心理学,認知科学など学際的な広がりをもちます.本研究室では,会話や会議などにおける人物行動の観測・センシング,人の行動や内面の数理モデルの構築と自動認識,テレプレゼンス(遠隔会議)等の応用システムの構築・評価など,入力?分析・処理?表現に至る範囲を研究対象と捉え,人-人,人-機械の間にて対話や共感を促進し,問題解決や合意形成を支援できるような人工知能の原理創出を目指しています. 研究プロジェクト
|
|||
 |
大槻研究室 Otsuki Lab |
エネルギーシステム,カーボンニュートラル,エネルギー経済,最適化 | |
大槻研究室 (エネルギーシステム研究室) 本研究室は2022年4月に誕生した研究室です。エネルギー需給の環境性・経済性・強靭性の観点から,世界や日本の最適なエネルギーシステムに関する研究を進めていきます。具体的にはエネルギー需給を模擬した数理モデル(主に最適化問題)を計算機上で構築し、数値計算を行います。他に類を見ないモデルを構築して、独自の視点から、国の政策や企業の意思決定に資する成果の発信に努めます。 研究プロジェクト
|
|||
 |
小原研究室 Obara Lab |
パワーエレクトロニクス, 電力ネットワーク | |
小原研究室 (パワーエレクトロニクス研究室) 本研究室は2021年4月に発足し、パワー半導体デバイスを用いた電力変換とその周辺技術、応用技術に関する研究を展開しています。パワーエレクトロニクスは、スマートフォンや家電のような小さなものから、メガソーラや周波数変換所などの発送電に使われる大きなものまで、非常に広範な電力容量で使われており、電力の有効利用に貢献しています。本研究室では、高度電力化社会を推進するクリーンな電力変換技術の創生を目指し、高効率な電力変換が当たり前になった現代において、電力変換装置の大量導入時代に求められる低ノイズ化、高信頼化、小型化、低コスト化、高度化の実現に挑んでいます。 研究プロジェクト
|
|||
 |
柯研究室 Ke Lab |
電気電子材料工学、電子デバイス、半導体プロセス工学、MOSFET | |
柯研究室(半導体電子デバイス研究室) 本研究室は2025年1月に発足しました。現在、CMOSの微細化は物理的限界に近づきつつありますが、AI・IoT時代を支えるため、当研究室では次世代半導体デバイスの研究に取り組んでいます。新しいチャンネル材料を用いたCMOSや、新しい原理・構造に基づく半導体デバイスの提案・実証を進めています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
久我研究室 Kuga Lab |
マイクロ波回路,移動体通信,電磁波工学,アンテナ | |
久我研究室 (マイクロ波回路研究室) 電磁波を使った通信装置や測定装置について、研究開発をしています。 |
|||
 |
小島研究室 Kojima Lab |
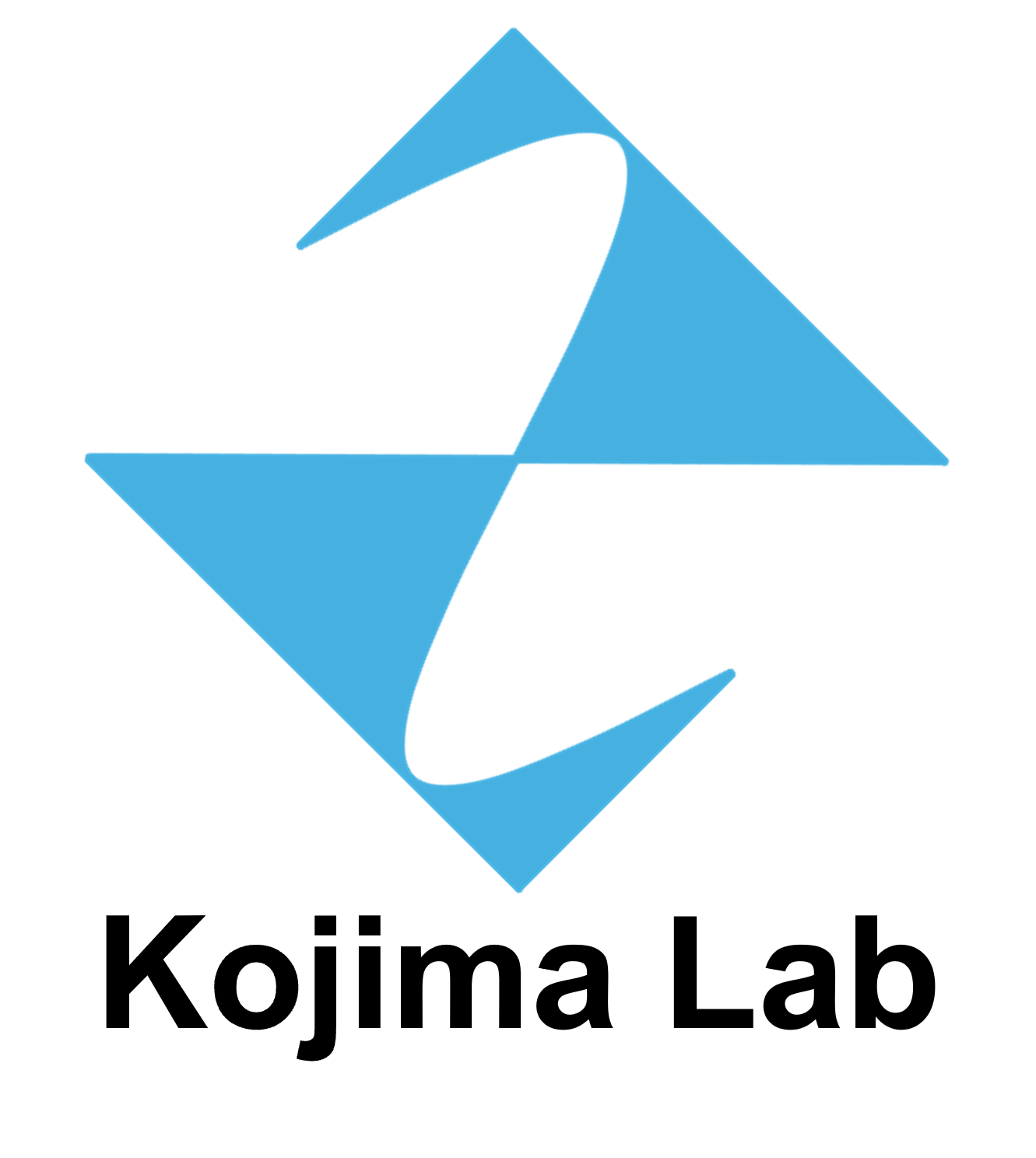 |
無線通信,機械学習,AI,情報理論,セキュリティ |
小島研究室 |
|||
 |
下野研究室 Shimono Lab |
ハプティクス,モーションコントロール,メカトロニクス,人間支援工学 | |
下野研究室 (モーションコントロール研究室) 人や環境とシステムとの間の相互作用を考慮した制御技術や、触覚情報を工学的に扱うハプティクス技術を研究しています。 |
|||
 |
佐野研究室 Sano Lab |
アンテナ工学,電磁波工学,マイクロ波工学 | |
佐野研究室 私たちの身の回りはスマートフォン、パソコン、ワイヤレスイヤホンをはじめとした無線機器であふれています。無線機器や通信量は増加の一途をたどっており、電磁波の周波数資源は今後ますますひっ迫していくことが予想されます。 本研究室では、電磁波の送受信に用いるアンテナの高性能化・多機能化に関する研究を行っています。これまでにあまり使われてこなかった高い周波数を用いるだけではなく、電磁波の放射方向や偏波などを巧みに操って、電磁波を賢く使うためのアンテナの実現を目指しています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
杉本研究室 Sugimoto Lab |
センシング,生体システム工学,人間情報通信システム,医療ICT, ITS | |
杉本研究室 (人間情報工学研究室) 先端ICT、センサ技術を活用し、生体機能計測・評価、感性認識モデル、BANシステム構築等の研究を行っています。 |
|||
 |
関口研究室 Sekiguchi Lab |
 |
スピントロニクス、マグノニクス、マグノニック結晶 |
関口研究室(スピントロニクス研究室) 人類の繁栄を支える「エレクトロニクス」は電子の持つ「電荷」を利用していますが、さらに電子の持つ「スピン」という磁石の源の性質を活用する工学応用や新しい物理現象を研究する領域が「スピントロニクス」(未来型電子工学)です。スピンを活用すると劇的に電気消費量が低減でき、また自然界からエネルギーを回収しながら動作するデバイス原理を構築できるため(エナジーハーベスティング)、省エネルギーで動作する論理演算デバイスや情報転送デバイスなどを作り出せると考えられています。本研究室では、ナノテクノロジー(マグノニクス、マグノニック結晶、磁気光学)を積極的に取り入れた応用展開で、この新分野に取り組んでいきます。 研究プロジェクト
|
|||
 |
孫研究室 Sun Lab |
深層生成モデル、ニューラルネットワーク、動画像圧縮、組込みシステム、集積回路 | |
孫研究室 (動画像処理研究室) 孫研究室は、2023年4月に誕生した新しい研究室です。本研究室では、画像処理とその高性能実装を中心に研究を中心とし、関連する広範囲な研究テーマに取組んでいます。学生はアルゴリズムからアーキテクチャまで幅広い技術に触れながら自分に最適な研究テーマを選ぶことができます。 現在、イギリス、中国などの有名な大学との共同研究を進めており、日本国内でも他大学(東京大学や早稲田大学など)と一緒にプロジェクトに参加しています。国際研究発信力を重視し、積極的に国際トップレベルの論文誌や学会で研究成果を発表していきます。 研究プロジェクト
|
|||
 |
竹村研究室 Takemura Lab |
データストレージ,ナノマグネティックス,バイオ・医療磁気 | |
竹村研究室 (マグネティックス研究室) 次世代の診断・治療をエレクトロニクスで開拓することを目指しています。ワイヤレスで駆動する体内マイクロロボット、磁場で効果を制御するがん治療や抗がん剤を初めとした薬剤など、バイオ・医療支援技術の研究開発に力を入れています。またIoTに不可欠なバッテリレス・モジュールやエネルギー・ハーベスティングに関してもオリジナリティの高い研究を実施しています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
辻研究室 Tsuji Lab |
電力システム工学,マイクログリッド工学,複雑系工学,非線形力学系理論 | |
辻研究室 電力技術と情報通信技術の融合により、人間のように自ら行動し、自己修復できるシステム構築を目指しています。 |
|||
 |
中田研究室 Nakata Lab |
人工知能,進化計算,機械学習 | |
中田研究室最適化問題とは、ある関数を最大化あるいは最小化する答えを見つける問題です。これは、実社会のあらゆる所に存在する重要な問題です。例えば、ロケットの性能(関数)を最大化する最適設計(答え)を見つけるにはどうすれば良いでしょうか。そもそも、膨大な数の考えうる設計候補から、人手で答えを見つけられるのでしょうか。できたとして、見つけた設計には、どのような新しい物理や法則が隠れているのでしょうか。 中田研究室では、より早く、より良い答えを見つける最適化技術、見つけた答えを分析しヒトが読みやすい形で知識化する機械学習技術を探求します。これらの技術によって、現在までヒトが知りえない革新的な答えが発見できる可能性が拓けます。さらに、発見した答えに潜む新たな法則を知識化することでヒトの知能増幅に貢献できます。 この研究目標に向けて、理論・手法研究から応用研究まで幅広く取り組みます。研究の方法論として、生物進化を模倣した進化計算と呼ばれる最適化技術をもとに研究を進めます。また、進化計算を応用した進化的機械学習技術を用いて、データ分析技術を構築しています。データ分析技術に限らず、同学習技術を発展させ、強化学習などを対象に、進化的適応能力を備えた自律性の高い進化的知能の基礎研究を行います。 研究プロジェクト
|
|||
 |
西島研究室 Nishijima Lab |
フォトニクス,プラズモニクス | |
西島研究室(光ナノマテリアル研究室) プラズモニクスは、金属と光の相互作用を利用したユニークなナノフォトニクスです。透明マントを実現する『メタマテリアル』や『メタ表面材料』、安心安全なセキュリティー技術やセンサーネットワークを支える新しいデバイスの核となる技術です。 私たちの研究室では、プラズモニクスの特性を利用して、『におい』(空気中の微量物質)を高感度に検出するセンサー、燃料電池社会を支える水素センサー、太陽電池や光熱電池を実現する光捕集アンテナ構造の構築などの様々な研究に対して、基本的な材料の探求からデバイスの構築、システムの開発まで、総合的な研究を展開しています。 そのほか新しいナノ材料の開発と応用に関する研究も幅広く行っています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
馬場研究室 Baba Lab |
フォトニック結晶,シリコンフォトニクス,ナノレーザ | |
馬場研究室(ナノ構造フォトニクス研究室) コンピュータは20世紀最大の発明の一つですが,その二乗のスピードで発展しているのが光通信です.地球規模のインターネットも,スマホなどの携帯端末も,光通信なくしては不可能です.もはや電力線と無線以外は光が情報を担う時代です.通信が圧倒的に高速になったことでコンピュータのクラウド化が加速,その超高性能とビッグデータを誰もが利用できるようになった結果,最近のAIやIoTが可能になりました.光通信はデータセンター内にも入り込み,最終的には集積チップの内部にまで到達しつつあります.その主役は電子と光を融合するシリコンフォトニクスです. モノとモノがつながるIoTでは,センサ,ネットワーク,クラウドが三大要素となり,社会の至る所にセンサが配置されるトリリオンセンサ社会が生まれようとしています.センサに関わる近未来の大きな話題の一つが自動運転です.これが実現されれば,自動車産業だけでなく,運送業,旅客業,観光業,宿泊業なども含め社会が大きく変革されます.これを実現するキーテクノロジーが車載センサです.周囲環境を取り込みAI処理やビッグデータ蓄積を可能とする3Dセンサ:光レーダー(LiDAR)が大きな注目を集めています.また,超高齢化が進み医療費が国家予算を揺るがすほど膨れ上がる中で,健康管理や治療を支えるバイオ医療センサの重要性も高まっており,そこでも光センサが主役の一つです. 本研究室は,長年研究し,世界を牽引してきたシリコンフォトニクスやナノフォトニクスをベースに,光通信と光センサの最先端機器を研究開発し,未来を創造する活動を行っています. 研究プロジェクト
|
|||
 |
濱上研究室 Hamagami Lab |
 |
知能システム,機械学習,自律分散システム,強化学習,マルチエージェント, 福祉支援システム |
濱上研究室 (知能システム研究室)人工知能(AI)と機械学習(ML)の要素技術・基礎理論を深化させ,持続可能な高度社会と人類の知的生産性の増大(Augmented Intelligence)に貢献する,「知能システムエンジニアリング」の創生をめざしています。 【人工知能と機械学習の基礎】近年大きな飛躍を遂げた人工知能と機械学習の技術をさらに高度化し,様々な分野でイノベーションの創出が期待できる画期的な知能化技術・理論の確立をめざしています。とくに,効率的・高速な学習アルゴリズムや,学習結果の再利用・転移のしくみを明らかにし,実環境でオンライン・ロバストに動作する知的要素技術を実現します。 【知的医療支援に関する研究】医療は高度な医学知識と多くのデータに基づく高度な知能システムであるという視点から,人工知能による医師の意思決定や業務を支援する様々な応用研究を進めています。特に,生活習慣病予防や未病対策にむけた知的ヘルスケア支援や,高度福祉など、人工知能による新たなライフサイエンスの高度化に貢献していきます。 【人工知能と機械学習の基礎】近年大きな飛躍を遂げた人工知能と機械学習の技術をさらに高度化し,様々な分野でイノベーションの創出が期待できる画期的な知能化技術・理論の確立をめざしています。とくに,効率的・高速な学習アルゴリズムや,学習結果の再利用・転移のしくみを明らかにし,実環境でオンライン・ロバストに動作する知的要素技術を実現します。 【知的医療支援に関する研究】医療は高度な医学知識と多くのデータに基づく高度な知能システムであるという視点から,人工知能による医師の意思決定や業務を支援する様々な応用研究を進めています。特に,生活習慣病予防や未病対策にむけた知的ヘルスケア支援や,高度福祉など、人工知能による新たなライフサイエンスの高度化に貢献していきます。 研究プロジェクト
|
|||
 |
福永研究室 Fukunaga Lab |
電磁波センシング,非破壊検査,文化財科学 | |
福永研究室 (非破壊センシング研究室) 人間の健康診断にX線や超音波の画像が用いられるように,外見だけではわからないモノの状態や内部構造を,様々な周波数帯域の電磁波を照射して反射・透過した信号を検出・画像化することにより観察する研究をしています。得られたデータを解析することで,モノの健全性を非破壊・非接触で診断することに有益な情報を抽出します。調査対象はインフラ設備,建造物,文化財など様々で,専門分野の境界のほとんどない活動をしています。国立研究開発法人情報通信研究機構,国立文化財機構奈良文化財研究所等,多くの研究機関・大学・企業と連携しており,特に絵画調査は国内外の美術館・博物館の所蔵品を美術史家・修復家と共同で調査しています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
藤本研究室 Fujimoto Lab |
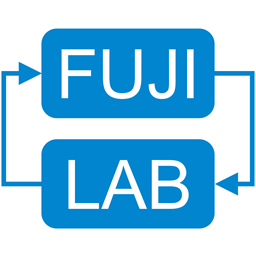 |
システム工学,ロボット工学,制御工学,離散事象システム |
藤本研究室 (システム制御研究室) 本研究室では主に,(1)システム最適化・自動化,(2)ロボティクス,(3)アクチュエータ,の研究に取り組んでいます。(1)は確率モデルや最適化アルゴリズムをベースに様々なシステムの最適化,予測,自動化を目指すもので,利用可能なデータの増大と計算コストの低下に伴い,幅広い応用が可能な分野です。計算機能力を活かした大規模最適化,移動ロボットや自動運転自動車の周囲環境認識・学習など知能化に関する研究を行っています。(2)は近未来に幅広い利用が予想される協働ロボットやパワーアシストロボット,福祉ロボットに関して,安全で柔軟な機構や運動制御の研究を行っています。(3)はモータを含む駆動システムの性能向上や省エネルギー化を目指すもので,新原理に基づくアクチュエータの設計・解析・開発を行っています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
水野研究室 Mizuno Lab |
 |
人工神経,スマートストラクチャ,光ファイバセンサ |
水野研究室 (センシングフォトニクス研究室)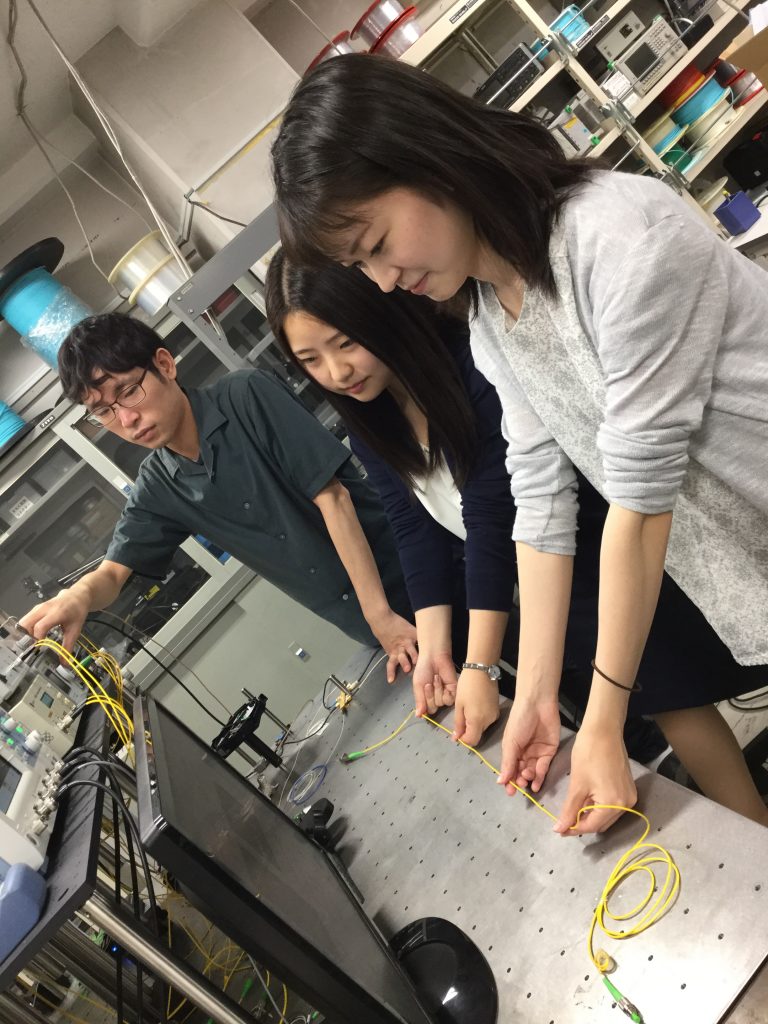 建物や橋、トンネル、ダムやパイプラインなど、さまざまな社会インフラの経年劣化や地震による損傷を正確に診断する技術の需要が高まっています。従来の電気センサは、大量の電気配線を必要とし、限られた箇所の情報しか得られないなどの課題がありました。そこで、光ファイバをさまざまな構造物に「神経」として埋め込もう、という取り組みが始まっています。この人工神経が機能すれば、その構造物自身が「ここが痛い」「ここが熱い」など、人間と同じような反応を示してくれることになります。このような構造物は、スマートストラクチャと呼ばれています。 本研究室では、スマートストラクチャを実現するための光ファイバセンシング技術について研究しています。特に注力しているのは、長い光ファイバに沿った任意の位置で伸びや温度などの計測ができる『分布型光ファイバセンサ』です。これまでに世界最高の空間分解能(どれだけ短い区間の伸びや温度が測れるか)と世界最高の動作速度を兼ね揃えるオリジナル技術の開発に成功しました。しかし、本技術の実用化のためには乗り越えるべき課題が多く残されており、更なる技術革新が望まれています。本研究室では、社会の安全・安心に貢献すべく、分布型光ファイバセンサの世界最高性能の追究を柱として研究活動を推進しています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
山梨研究室 Yamanashi Lab |
 |
超伝導エレクトロニクス、ニューロモルフィック回路、量子コンピュータ |
山梨研究室(超伝導量子集積エレクトロニクス研究室) 現在の集積回路は回路中の電子の動きを制御することで動作していますが、この方法での性能向上は限界に近づいています。 そこで従来の集積回路に代わる新しい回路技術が強く求められています。 本研究室では、物質を低温にしたときに発現する超伝導現象を用いた情報処理システムの研究を行っております。超伝導素子は短い応答時間、超低消費電力性、磁場や電流に対する極めて高い感度、巨視的な量子効果が利用可能である、といったエレクトロニクスの観点からとても魅力的な特徴を持っています。これらの特徴を利用した、従来にはない優れた情報処理技術の確立を目指しています。 超伝導現象を使って初めて可能になる100ギガヘルツを超えるクロック速度での超高速低電力演算や、特定の問題を従来の計算に比べて桁違いの速度で解くことができる量子計算回路や生体模倣回路の応用に関する研究を行っています。 研究プロジェクト
|
|||
 |
吉川研究室 Yoshikawa Lab |
 |
集積回路工学,超伝導エレクトロニクス,電子デバイス |
吉川研究室(集積エレクトロニクス研究室) 新しい動作原理に基づく電子デバイスを用いて、次世代の高速・低消費エネルギー大規模集積回路(VLSI)システムを実現するのが本研究室の目標です。 例えば超伝導現象を利用すれば、単一磁束量子(磁束の最小単位)を情報の1ビットに用いる超高速ディジタル回路を作ることができます。これらの回路は、100 GHzを超えるクロック周波数で動作し、半導体回路の数千分の1の電力で演算を行なうことができます。また、回路を断熱的、双方向的に動作させる可逆論理回路を用いれば、無限小のエネルギーでの情報処理が可能となります。半導体VLSIにおいては、動作温度をマイナス200度付近まで冷却すると、動作スピードが向上し、演算スピードを飛躍的に高めることができます。一方、デバイス自体の機能が新しくなると、これらの機能を生かすために、新しい回路アーキテクチャやコンピュータアーキテクチャの検討も必要になります。 我々は、VLSIシステムを、新たなデバイスの動作原理、アーキテクチャならびに設計手法という多方面から眺め、高性能情報処理システムの実現を目指した研究を行っています。 研究プロジェクト
|
|||